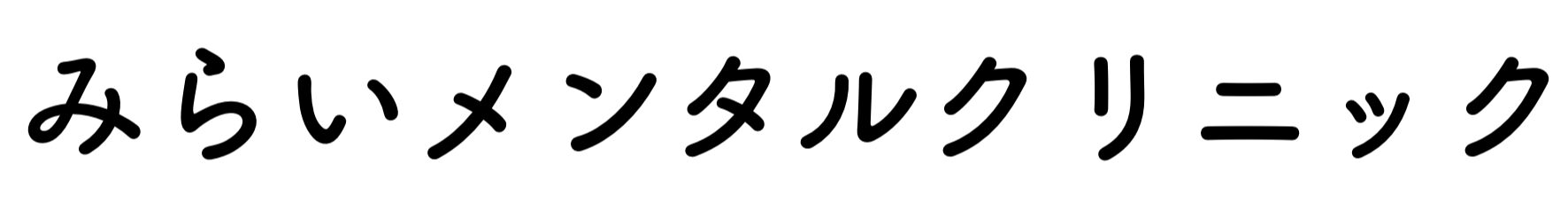はじめに
こんにちは。精神科医として心の健康に関する情報を発信している、精神科医ブロガーのやっくん(@mirai_mental)です。
今回は、統合失調症に特徴的にみられる「連合弛緩」について解説していきます。
思考の障害の種類
まず、思考の異常は、教科書的には①思路の異常、②思考体験の異常、③思考内容の異常に分けられるといわれています。
思考の異常の種類
- ①思路の異常・・・連合弛緩、思考制止、観念奔逸など
→思考の過程の異常。まとまりを欠いたり、異常に亢進したり制止してしまう。 - ②思考体験の異常・・・思考伝播・自生思考・強迫観念など
→自我が障害され、思考を自分でコントロールできなくなる。 - ③思考内容の異常・・・妄想着想・妄想知覚・被害妄想など
この中でも、「連合弛緩」は「思路の異常」、つまり思考の過程に異常が生じるタイプに分類されます。
連合弛緩とは
連合弛緩とは、思考における観念同士の結びつき(連合)が、ゆるくなってしまう状態を指します。
通常、私たちの思考は「意味のある関連性」を持って、次から次へと展開していきます。鉛筆が、バンドによって束ねられたような状態ともたとえられるでしょうか。
しかし、連合弛緩が起きると、意味的なつながりが緩くなり、脱線したような思考展開になってしまいます。つまり、一見つながっているようで、よく聞いてみると論理的なつながりが破綻してしまっている、という状態になります。
例えば、
「オムライスを作ろうと思っていたけど、今日は雨だったから、犬がかわいそうで、地球の環境問題を考えないといけないんだよね。」
というふうに、話の論理的な連続性が失われ、脈絡のない飛躍が生じます。
このように、連合弛緩では「思考のまとまり」がなくなってしまうため、周囲から見ると話が支離滅裂に感じられるのが特徴です。
思考の解体がさらに進展すると
「連合弛緩」の場合は、まだ意味のあるつながりがのこっていることもありますが、さらに解体が進むと、支離滅裂になり、まったく無関係な言葉の羅列になってしまうことがあります。
これを、「言葉のサラダ」という言い方でたとえることがあります。サラダには、ボウルにそれぞれの種類の野菜が入っていますが、混ざり合うことはなく、野菜の形がそのまま残っています。
それにたとえて、「言葉のサラダ」と呼ばれているのです。
連合弛緩と観念奔逸の違い
また、躁状態にみられる「観念奔逸」とも区別が必要です。
観念奔逸では思考のスピードが異常に速くなり、どんどん新しい話題に飛んでいくものです。
一方、連合弛緩では「意味的なつながり自体」が緩んでいるため、話の筋が理解できなくなってしまうのです。
おわりに
今回は思考の障害の種類と、その中でも「連合弛緩」について解説してみました。思考障害の理解は、統合失調症の診断や病態理解のうえでとても重要なポイントになります。
国家試験や臨床の現場でも頻出の知識なので、ぜひ整理しておきましょう!
まとめ
- 「連合弛緩」は思路の障害の1つ。
- 統合失調症でみられ、思考のまとまりが失われる状態。
- 観念の連続性が保たれず、話が飛躍したり脈絡がなくなってしまう。
- 観念奔逸など、似た用語と区別して理解しておくことが重要。