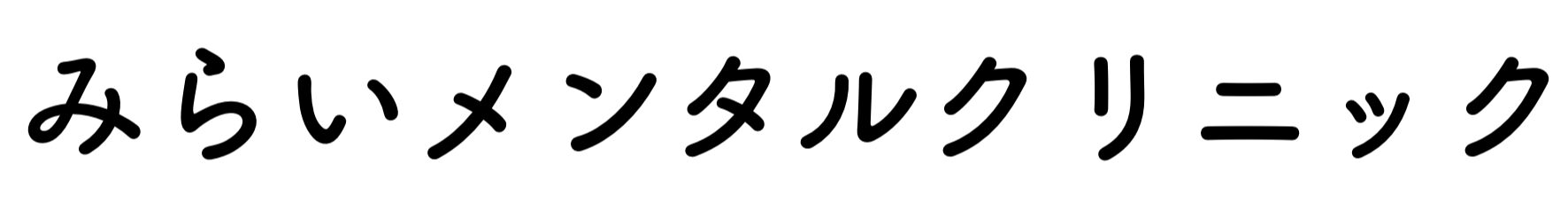はじめに
こんにちは。精神科医として心の健康に関する情報を発信している、精神科医ブロガーのやっくん(@mirai_mental)です。
今回は、思考体験の異常のひとつである「自生思考」について、精神科医の視点からわかりやすく解説していきます。
思考の障害の種類
精神医学において、思考の異常は大きく3つに分類されます。
- ①思路の異常
(連合弛緩、思考制止、観念奔逸など)
→ 思考の進み方やまとまりの異常。 - ②思考体験の異常
(考想伝播、思考奪取、自生思考など)
→ 思考そのものに対する自己感覚(自我意識)が障害される。 - ③思考内容の異常
(妄想、被害妄想、誇大妄想など)
→ 思考の「中身」に異常が現れる。
このうち、「自生思考」は②思考体験の異常に分類されます。
自生思考とは?
自生思考とは、
自分の意思とは無関係に、考えが自然に湧き上がってきてしまうと感じる体験のことを指します。
たとえば、
- 「考えようと思ったわけではないのに、勝手に考えが浮かんでくる」
- 「自分の意志でコントロールできない思考が頭に流れ込んでくる」
といった感覚です。
通常、私たちは「自分が考えようと思って考える」という感覚を自然に持っていますが、
自生思考では、その「思考の主体感」が失われてしまうのが特徴です。
なぜ自生思考が起こるのか?
自生思考は、主に統合失調症に見られる自我障害のひとつとされています。
通常なら、
- 「この考えは自分が生み出したものだ」
という感覚(思考の自己性)が保たれています。
しかし統合失調症では、この自己性が障害されるため、
- 「自分の考えのはずなのに、自分で作ったものではない」
- 「考えが勝手に湧き上がる」
と感じる異常体験が生じます。
自生思考は、思考が外部から入り込んだわけではない点で、考想吹入とは異なります。
あくまで自分の内側から自然に湧き上がるのですが、そのコントロール感が失われているのです。
自生思考と似た症状との違い
思考吹入(思考挿入)との違い
- 自生思考
→ 自分の内側から勝手に思考が湧き上がる感覚。
(でも「外部から入ってきた」という感覚はない) - 思考吹入(思考挿入)
→ 他人や外部の存在によって思考が送り込まれたと感じる。
(「外から来た」という強い感覚がある)
つまり、自生思考は「内発的だけどコントロールできない」、思考吹入は「外部から押し込まれる」という違いがあります。
とはいえ、思考吹入に関しては、統合失調症で見られることが多い症状なので、特には自生思考や思考吹入の症状が混在していることもあると考えられます。
強迫観念との違い
- 自生思考
→ 自然に湧いてきてしまう思考。必ずしも反復的ではない。 - 強迫観念
→ 本人が不合理だとわかっていても、繰り返し侵入してきて苦痛を感じる思考。
神経症で見られる強迫観念と自生思考は似ていますが、強迫観念の特徴は、本人が不合理性を自覚していて、それでも抑えられることができない点が特徴です。
おわりに
今回は、「自生思考」について精神科医の視点から解説しました。
自生思考は、思考に対するコントロール感の喪失という、自我障害の中核的なサインのひとつです。
本人にとっては非常に不思議で不安な体験ですが、正しく理解し、丁寧に対応することが大切です。
精神科医療では、こうした症状の背景にある脳の変化や自己感覚の障害を踏まえた治療が行われます。
まとめ
- 自生思考は、思考体験の異常のひとつ。
- 自分の意思とは無関係に、思考が自然に湧き上がってくる感覚。
- 統合失調症に伴う自我障害の一部と考えられる。
- 思考吹入や強迫観念との違いを理解することが重要。