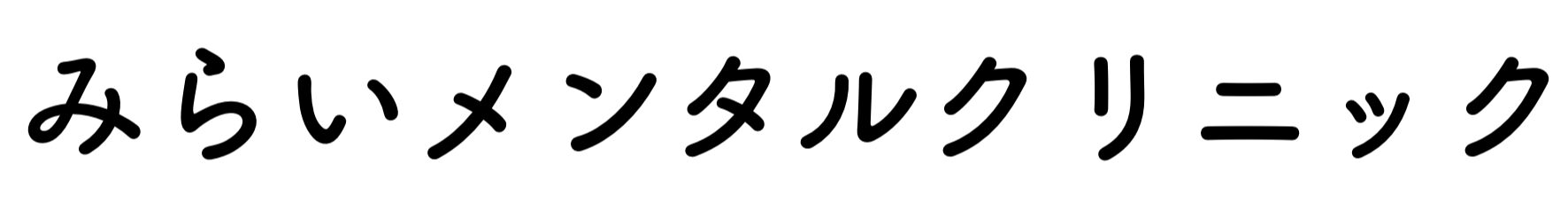はじめに
こんにちは。精神科医として心の健康に関する情報を発信している、精神科医ブロガーのやっくん(@mirai_mental)です。
今回は、「夕暮れ症候群(サンダウニング)」について、精神科医の立場からわかりやすく解説していきます。
そもそも「夕暮れ症候群(サンダウニング)」とは?
夕暮れ症候群とは、
夕方から夜にかけて、認知症の方に不安や混乱、興奮が強く現れる現象を指します。
英語では、その名前の通り、Sundowning(サンダウニング)と呼ばれています。
具体的な症状としては、
- 夕方になると落ち着きがなくなる
- そわそわと歩き回る
- 家族や介護者に対して怒りっぽくなる
- 幻覚や妄想が出ることもある
こうした症状が日中よりも夕方以降に悪化するのが大きな特徴です。
なぜ夕方になると悪化するの?
夕暮れ症候群(サンダウニング)が起こる正確なメカニズムはまだ完全にはわかっていませんが、
次のような要因が関与していると考えられています。
- 脳内時計(概日リズム)の乱れ
→ 認知症によって体内リズムが崩れ、夕方に不調が目立つ。 - 光の変化に対する脳の感受性の変化
→ 日が沈んで周囲が暗くなることで、不安感や混乱が強まる。 - 日中の疲労やストレスの蓄積
→ 夕方までの活動による疲労が、混乱や興奮を引き起こす。 - 認知機能の低下による周囲状況の誤認
→ まわりの状況をうまく理解できず、不安が高まる。
つまり、単なる「気分の問題」ではなく、脳の生理的変化と環境要因が重なって生じる現象といえます。
夕暮れ症候群(サンダウニング)への対応方法
夕暮れ症候群の要因の大きなものの一つに、体内時計(概日リズム)の乱れがあると考えられています。
ご高齢の認知症の方は、どうしても日中に寝てしまったり、昼夜逆転傾向になってしまうことが多いものです。
そのリズムを整えるには、地道ではありますがコツがあります。
生活リズムを安定させる
- 起床や就寝時間はある程度一定にする
- 昼寝をしすぎない(30分程度)
- 朝にしっかり太陽光を浴びる
- 日中に適度な活動(軽い運動や散歩)を取り入れる
とくに、朝起きたら太陽の光を浴びることで、脳に「今は朝なんだ」と認識させることができるので、体内時計の乱れを整える大きな武器になります。
また、体を軽く動かしたり、水分や食事を摂り、おなかにも「活動開始の時間だ」と認識させてあげることも役に立ちます。
本人の安心感を高める
- 不安を否定せずに寄り添う
- 「大丈夫だよ」「ここにいるよ」とやさしく声をかける
場合によっては、主治医と相談の上、薬物療法(軽い抗不安薬、睡眠導入薬など)を検討することもあります。
環境を整える
家族だけではなかなか環境を整えることができないときは、プロに任せるのも一つの選択肢です。
デイサービスなどの介護福祉サービスを利用することで、決まった時間に起きて、活動するリズムが見につきます。
また適度な運動や、社会的かかわりをもつという意味でも、症状の改善に役に立つ可能性があるといえます。
おわりに
今回は、「夕暮れ症候群(サンダウニング)」について精神科専門医の視点から解説しました。
夕暮れ症候群は、認知症の方本人にとっても、支えるご家族にとっても負担を感じることのある現象ですが、
正しく理解し、環境を工夫することで症状を和らげることが可能です。
大切なのは、
- 本人の不安な気持ちを否定しないこと
- 安心できる環境を整えること
焦らず、できることから一つずつ取り組んでいきましょう。
また、家族でケアがしきれないときは、精神科医に相談してみることも一つの考えだと思います。
まとめ
- 夕暮れ症候群(サンダウニング)は、夕方以降に認知症の方の不安・混乱・興奮が強まる現象。
- 脳内時計の乱れ、光の変化、疲労などが原因と考えられている。
- 環境調整と生活リズムの安定が、症状の緩和に役立つ。
- 困ったときは主治医に相談しながら、無理なく対応していくことが大切。